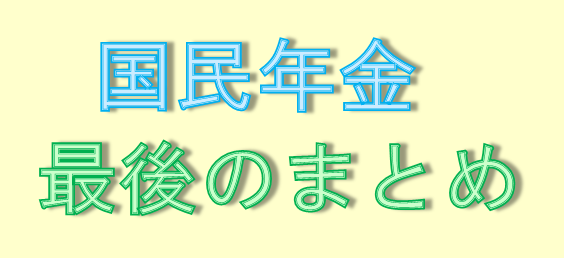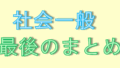明日が試験なら最後に何を復習するか?科目ごとにまとめました。
今回は国民年金です。
模試で出題された論点や私がよく間違える論点をまとめています。
学習の点検としてご利用くださいm(_ _)m
※国民年金は厚生年金と比較しながら学習すると理解が深まります。
届出等
第1号被保険者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、当該事実があった日から14日以内に、市町村長に届け出なければならない。
→14日以内です。厚生年金の受給権者が死亡したときは、10日以内に、厚生労働大臣に届け出なければなりません。
国民年金原簿
国民年金原簿の記録事項に、個人番号は含まれない。
→個人番号は記録事項に含まれません。厚生年金原簿も含まれません。
国民年金原簿の記録事項には「種別の変更」がある。
→その通りです。個人的に迷うのが調査で、厚生労働大臣は被保険者に対し「出産予定日」の情報を(産前産後免除のため)、受給権者に対しては「身分関係、障害の状況」に関する書類の提出を命じることができるという条文と混同します。
被保険者
第3号被保険者であった者は、第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったことについて、当該事実があった日から14日以内に、被扶養配偶者非該当届を厚生労働大臣(日本年金機構)に届け出なければならない。
→厚生労働大臣です。市町村長ではありません。種別変更届は市町村長へ提出します。
被扶養配偶者非該当届は、離婚か、第3号被保険者の収入増のときに提出が必要です。
保険料
産前産後免除に係る届出は出産予定日の6月前から行うことができる。これに期限はない。
→6ヶ月前から行うことができます。届出の期限はありません。
地方税法に規定する障害者、寡婦又はひとり親等であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が135万円以下であるときは、申請免除の対象者となる。
→135万円です。健康保険法の被扶養者の生計維持関係の要件は年間収入130万円(60歳以上又は障害者は180万円)と混同してしまいました…。
保険料全額免除の所得基準は、単身の場合は67万円である。
→その通りです。全額免除と部分免除で計算式が異なる(35万円?32万円?38万円?)ので微妙に覚えにくいですが、67万円を覚えれば「35万円+32万円ね。ということは部分免除は38万円か」と導けるかなと思います。扶養控除申告書に馴染みのある人は38万円がすぐ浮かぶかと。
全額免除は扶養親族の数に1を足しますが、部分免除は足さずに38万円×人数です。
障害基礎年金や遺族基礎年金の受給権者は、追納することができる。
→その通りです。老齢基礎年金の受給権者は追納することができません。
申請による保険料の全額免除について、学生等である期間及び学生等であった期間は除外されている。
→学生納付特例は申請免除に対しては優先されます。「法定免除」は学生納付特例より優先されます。
老齢
振替加算の受給者は、遺族厚生年金を受けることができるときであっても、支給停止されることはない。
→支給停止されません。障害基礎年金や障害厚生年金を受けることができるときは支給停止されます。
障害
20歳前傷病の障害基礎年金は、前年の所得が370万4千円を超え472万1千円以下のときは1/2が支給停止され、472万1千円を超えるときは全額支給停止される。
→その通りです。数字は覚えなくていいと思いますが、少なくとも「なんだこれ?初めて見たぞ…」という状態は避けたいかなと。見慣れない数字なので本番で出たら焦りそうです。
旧法による障害年金の受給権者には、事後重症による障害基礎年金は支給されない。
→支給されません。ただし、経過措置による障害基礎年金の支給を受けることはあります。
第1号被保険者の独自給付
寡婦年金の夫の支給要件は、納付済期間だけでなく免除期間も含む。学特と納付猶予は含まない。
→保険料免除期間もOKです。合算対象期間は含みません。65歳未満の任意加入被保険者の期間は含みますが、65歳以上の特例任意加入保険者の期間は含みません。
死亡一時金に改定率は乗じられない。
→期間に応じて12~32万円です。改定率の適用はありません。
寡婦年金と死亡一時金に国庫負担はありません。付加年金は4分の1、死亡一時金に付加される8,500円は4分の1が国庫負担です。
→覚えましょう。大した論点ではありませんが、不意に忘れてしまったり勘違いするのが怖いです。
国民年金基金
国民年金基金の年金・一時金は、譲渡、担保、差し押さえることができない。
一時金は租税その他公課を課すことはできないが、年金は課すことができる。
→通達より。覚えましょう。
社労士になりたいブログパープル2.png)