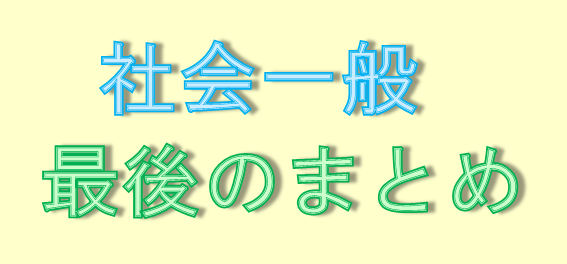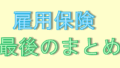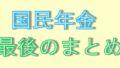明日が試験なら最後に何を復習するか?科目ごとにまとめました。
今回は社会一般常識です。
模試で出題された論点や私がよく間違える論点をまとめています。
学習の点検としてご利用くださいm(_ _)m
国民健康保険法
○国は都道府県に対して、調整交付金を交付する。
→市町村ではありません。国は32%を療養給付費等負担金として負担します。
○出産育児一時金は法定任意給付である。
→法定任意給付は他に、葬祭費、葬祭の給付があります。任意給付には傷病手当金、出産手当金があります。
高齢者医療確保法
○医療に要する費用の適正化を図るための取り組みにおいては、都道府県は中心的な役割を果たす。
→市町村ではありません。国は「必要な各般の措置を講ずる」、地方公共団体は「所要の施策を実施しなければならない」です。
○医療費適正化基本方針は6年ごとに6年を1期、特定健康診査等基本方針も6年ごとに6年を1期。
→6年です。5年ではありません。医療費適正化基本方針は「全国医療費適正化計画」「都道府県医療費適正化計画」、特定健康診査等基本方針は「特定健康診査等実施計画」です。5年ごとに5年を1期は次世代法の行動計画策定指針です。
○市町村は、後期高齢者医療の事務を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合を設ける。
→「都道府県」ではありません。
○都道府県ごとに保険者協議会を組織する。
→都道府県ごとに必ず設置します。以下の業務を行います。ちなみに国民健康保険は、都道府県にも市町村にも協議会を置きます。
・特定健康診査等の実施、高齢者医療制度の運営その他の事項に関する保険者その他の関係者間の連絡調整
・保険者に対する必要な助言又は援助
・医療に要する費用その他事項に関する情報についての調査及び分析
・都道府県医療費適正化計画の実績の評価に関する調査及び分析
○後期高齢者医療広域連合が被保険者に対して課する保険料の賦課額は、80万円を超えることができない。
→令和7年度の保険料の賦課限度額は80万円です。
介護保険法
○市町村は、保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者等が、納期限から1年が経過するまでの間に保険料を納付しない場合においては、被保険者証に、支払方法変更の記載をする。
→支払方法変更の記載です。国民健康保険は、被保険者証を返還させ被保険者資格証明書を交付、特別療養費の支給でした。(国民健康保険証が廃止されたため、現在は特別療養費の支給に関する通知です)
○市町村介護保険事業計画は3年を1期とする。
→都道府県介護保険事業支援計画も3年を1期とします。
○市町村は、地域ケア会議を置くよう努めなければならない。
→努力規定です。地域ケア会議とは、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に掲げる事業の効果的な実施のために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体により構成される会議です。
○市町村は、居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護支援を受けたときは、居宅介護サービス計画費を支給する。
→覚えましょう。と言いたいところですが。介護給付と予防給付は似たような名前かつ数が多いので「居宅介護サービス計画費」だけ押さえればいいかなと思います。原則として、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額です。
確定拠出年金法
○簡易企業型年金の商品提供数は2本以上35本以下。
→通常の企業型年金は3本以上35本以下です。
確定給付企業年金法
○租税その他の公課は障害給付金として支給を受けた金銭を標準として課することができない
→その通りです。また、確定給付企業年金の受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
ただし、老齢給付金、脱退一時金及び遺族給付金を受ける権利を国税滞納処分により
差し押さえる場合は、この限りではありません。
こちらは模試で出題されましたが細かい論点だと思います。
○確定給付企業年金の掛金の額は、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならず、事業主等は、少なくとも5年ごとに掛金の額の基準に従って掛金の額を再計算しなければならない。
→5年です。6年ではありません。社一もたくさん数字出てきますね。。
社労士になりたいブログパープル2.png)