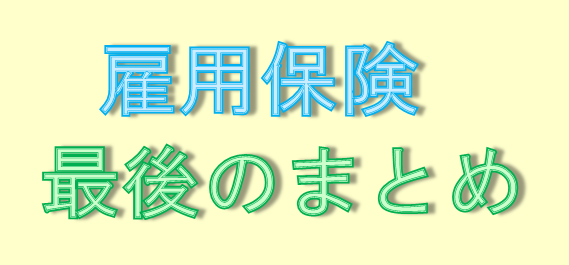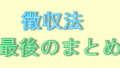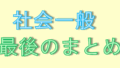明日が試験なら最後に何を復習するか?科目ごとにまとめました。
今回は雇用保険法です。
模試で出題された論点や私がよく間違える論点をまとめています。
学習の点検としてご利用くださいm(_ _)m
被保険者
特定漁船以外の漁船に乗り組むために雇用される被保険者は、原則として被保険者とならない。
→「特定漁船」は1年を通じて稼働する漁船と覚えましょう。つまり雇用保険の被保険者となります。少しコアな論点ですが、船員は各科目横断しておきましょう。
自動変更対象額
賃金日額の最低限度額は、年齢に関わらず一律。最高限度額で最も高額なのは45歳以上60歳未満。
→覚えましょう。45歳以上65歳未満ではありません。「45歳以上60歳未満」の最高限度額は、介護休業給付金の休業開始時賃金日額の上限額に使われています。
自動変更対象額は、10円未満四捨五入である。また、最低賃金日額に達しないものは、当該年度の8月1日以後、当該最低賃金日額とされる。
→1円単位ではありません。労災保険法の自動変更対象額も10円未満四捨五入です。ちなみに労災の給付基礎日額は1円未満”切り上げ”です。
特定受給資格者
予期し得ず、離職の日の属する月以後6ヶ月のうちいずれかの月に支払われる賃金の額が、当該月の前6ヶ月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなった場合は、解雇等により離職した者として特定受給資格者となる。
→100分の85です。特定受給資格者です。
賃金(退職手当を除く)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかった場合は、解雇等により離職した者として特定受給資格者となる。
→3で除すので1/3ですね。30%ではありません。1/3なので33%ぐらいですね。3割か1/3かで迷ったら多い方(33%>30%)と覚えましょう。
雇用継続給付
初めて高年齢再就職給付金を受けようとする場合、再就職後の支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内に、必要書類を公共職業安定所長に提出しなければならない。
→2ヶ月ではありません。4ヶ月以内です。高年齢雇用継続基本給付金も4ヶ月以内です。提出する書類について、「60歳到達時賃金証明書」は高年齢雇用継続基本給付金は必要で、高年齢再就職給付金は不要です。
また育児休業給付金の申請も「4」ですが、こちらは「支給単位期間の初日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで」となっています。さらに言うと、介護休業給付金は2ヶ月です…。
高年齢雇用継続基本給付金:支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内
高年齢再就職給付金:再就職後の支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内
介護休業給付金:介護休業を終了した日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで
育児休業給付金:支給単位期間の初日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで
育児休業等給付
出生後休業支援給付金の額(13%)は、育児休業給付の額(67%)と合わせて80%相当額となるように設計されている。
→休業開始前賃金の80%を受け取れるということで、手取りの10割相当が受け取れるということですね。なかなか手厚い。
期間雇用者の育児休業給付金の支給要件に「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件はない。
→以前はありましたが現在はありません。
育児休業給付金について、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子が1歳6ヶ月(一定の場合は2歳)に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者でなければならない。
→介護休業給付金は「93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までに、その労働契約が~」、出生時育児休業給付金は「8週間を経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日までに、その労働契約が~」です。
給付制限
離職理由による給付制限期間中は、失業の認定を行う必要はない。
→失業の認定は行われません。「待期期間」は失業の認定は行われます。
離職理由による給付制限期間中に、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等の受講をしたら、受講期間及び受け終わった日後の期間、給付制限は解除される。
→覚えましょう。自己都合退職の場合は、離職日前1年以内に受講していた場合も、制限が解除されます。
雇用保険二事業
雇用関係助成金は、過去5年以内に偽りその不正の行為により、給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主には支給されない。
→5年です。3年ではありません。健保の保健医療機関等の指定の拒否と同じですね。
社労士になりたいブログパープル2.png)