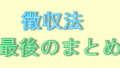私がよく間違えたりうろ覚えな論点を81項目紹介します。
学習の点検としてご利用ください。
サムネに深い意味はありません。ちいかわが2025年に試験に合格したのであやかります(^ω^)
労働基準法
解雇制限を受ける労働者について、たとえ労働者の責に帰すべき事由が判明しても、その者を解雇制限期間中には解雇することはできない。
→例えば妊産婦が横領などをしても解雇できないということですね。
日日雇い入れられる者には解雇の予告の規定は適用されないが、その者が1か月(×30日)を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
→雇用保険法の「継続して31日以上雇用されることが見込まれない者」など、「1月」「31日」「30日」はしっかり押さえたいです。
労働基準法第39条第6項に定めるいわゆる労使協定による有給休暇の計画的付与については、時間単位でこれを与えることは認められない。
→覚えましょう。
使用者は、労働基準法第33条の「災害その他避けることのできない事由」に該当する場合であっても、同法第34条の休憩時間を与えなければならない。
→災害時なのだから休まず働く、とはならないということですね。
所轄労働基準監督署長(×都道府県労働局長)は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。
→命ずることができるなんて、なかなか強い権限を持っていますね。就業規則は労基に届け出るという知識と紐づければ「都道府県労働局長」という引っ掛けは避けられるかなと思います。
貯蓄金管理規程は、労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならないのであり、「行政官庁(労働基準監督署長)へ届け出る」のではない。
→規定は周知し、労使協定は届け出ます。
フレックスタイム制を実施する際には、清算期間が1ヶ月を超える場合に限り、労基法に掲げる事項を定める労使協定を行政官庁に届け出なければならない。
→逆に言うと「清算期間が1ヶ月以内であれば届出は不要」ということです。
未成年者の労働契約の解除ができる者に、学校長は含まれていない。
→親権者、後見人、所轄労基署長は解除することができます。
高度プロフェッショナル制度の規定は、満18歳に満たない者については、適用されない。
→専門業務型や企画業務型は特に規定がないみたいです。基本的に年少者が就くという想定ではないのでしょう。
安全衛生法
作業環境測定を行った場合に、行政官庁へのその結果の届出義務はない。
→作業環境測定は測定の頻度や記録の保存は決められていますが、届出は不要です。
クレーン検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録性能検査機関(×労基署)の性能検査を受けなければならない。
→「登録性能検査機関」は厚生労働大臣の登録を受けた者です。性能検査は、検査証の更新時に受けます。
特定機械等(建設用リフトを除く)で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、当該特定機械等について、労働基準監督署長(×都道府県労働局長)の検査(使用再開検査)を受けなければならない。
→落成検査は労基署長、移動式の製造時等検査は都道府県労働局長です。
労災保険法
労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定めるところによって所轄労働基準監督署長(×都道府県労働局長 ×労働基準局長)が算定する額を給付基礎日額とする。
→給付基礎日額の特例です。私傷病、じん肺、船員などがあります。
葬祭料は、スライド制の適用においては、遺族補償一時金とみなされ、年金給付基礎日額のスライド制が適用される。
→覚えましょう。休業、年金、一時金、特別加入の給付基礎日額について、スライドと最低・最高額の判別はできますか?
休業補償給付に係る給付基礎日額の改定における「平均給与額」は、毎月勤労統計の「毎月きまって支給する給与」の四半期における労働者1人当たり1か月平均額をいう。
→労災では他に「賃金構造基本統計」が登場します。
スライド制は毎月勤労統計、年齢階層別の最高・最低限度額は賃金構造基本統計。
→そのまま覚えてしまいましょう。
若年支給停止者であっても、遺族補償年金前払一時金を請求することはできる。
→生活保障という意味合いでしょうか。こんなの、絶対一時金をもらった方が得ですよね。
特別支給金には被災労働者の損害を填補する性質を有するということはできず、したがって、第三者行為災害の場合に、第三者から損害賠償を受けたときであっても、特別支給金は損害賠償と調整されない。
→あと、特別支給金は労審法の不服申立の対象ではないことも押さえておきましょう。
老齢厚生年金や老齢基礎年金については労災保険のいずれの年金とも併給調整が行われることはない。
→老齢年金をもらいながら働いている人が仕事中に負傷したと考えると、調整されるのは理不尽ですよね。
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
→物価の安い海外から日本に働きに来て、わざと怪我をして障害年金をもらうということがあったみたいです。
特別加入した中小事業主に係る業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害の認定は、厚生労働省労働基準局長(×労働基準監督署長)が定める基準によって行うものとされる。
→災害の認定なんて労基署長のような感じもしますが、厚生労働省労働基準局長です。一人親方等も同様ですが、海外派遣者は国内の労働者に準じて取り扱われます。
日本企業の海外支店に現地採用された者は、特別加入することができない。
→当たり前といえば当たり前ですが。現地の日本人は?など余計なことを考えてしまいます。
二次健康診断等給付については、事業主からの費用徴収は行われない。
→そのまま覚えましょう。
雇用保険法
所定労働時間を短縮することによる就業をした場合(雇保1条 令和7年改正)
→今年改正があった目的条文ですので、確実に押さえる内容です。
雇用保険法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業主の事業については、その数のいかんにかかわらず、適用事業として取り扱う必要はない。
→例えば20時間未満の労働者のみを200人雇用していても、適用事業所とは扱わないということですね。
受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入の1日分に相当する額から控除額を控除した額と基本手当日額の合計額が賃金日額の100分の80相当額を超えなければ、基本手当は減額されずに支給される。
→覚えましょう。
60歳以上で定年退職した者に対する雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間の延長は、1年を限度とする。
→定年して少しゆっくりしたい人向けでしょうか。
広域延長措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当の支給を受けることができる者が厚生労働大臣が指定する地域(指定地域)に住所又は居所を変更した場合には、引き続き当該措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。なお、延長できる日数の限度は移転前後を通じ90日である。
→全国延長給付も90日です。
常用就職支度手当は、給付制限期間が経過した後であっても、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いた場合でなければ、支給されない。
→常用就職支度手当の受給要件です。
広域求職活動費の支給申請書の提出は、広域求職活動を終了した日の翌日から起算して10日以内にしなければならない。
→開始前ではなく、終了してからの申請です。
受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所長の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して10日以内に、求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書に受給資格者証等を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
→1つ前と同じ論点ですね。
受給資格者が基本手当について離職理由に基づく給付制限を受けているが、その制限の期間内に広域求職活動を開始した場合には、広域求職活動費を受給することができる。
→かつては制限期間中は受給できなかったみたいです。
専門実践教育訓練を開始した日における年齢が45歳以上の者は、教育訓練支援給付金を受けることができない。
→専門実践教育訓練は中長期的なキャリア形成に資する教育訓練ですので、年齢制限があるのでしょう。
高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の64(×75)に相当する額未満であるときは、原則として、当該支給対象月に支払われた賃金の額に、100分の10を乗じて得た額とされる。
→高年齢雇用継続基本給付金とほぼ同じです。支給要件に「100分の75」と出てくるので混同しないよう注意です。
受給資格者が当該受給資格に基づく基本手当を受けたことがなくても、傷病手当を受けたことがあれば、高年齢再就職給付金を受給することができる。
→傷病手当を受けたときは、基本手当の支給を受けたものとみなされます。
介護休業給付金の額は、一支給単位期間(当該介護休業を終了した日の属する支給単位期間を除く)について、休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の67に相当する額とする。
→高年齢雇用継続給付は「100分の75」と「100分の64」でしたが、介護休業給付は「100分の80」と「100分の67」ですね。。
日雇労働被保険者が普通給付の日雇労働求職者給付金に係る失業の認定を受けようとする場合において、失業の認定を受けようとする日が、行政機関の休日に関する法律に規定する行政機関の休日であって、かつ、公共職業安定所が日雇労働被保険者の職業紹介について、平常どおり業務をおこなわない日であるときは、その日に係る失業の認定は届出によって行うことができる。
→そうなんだ~という感じです。
日雇労働求職者給付金の特別給付:継続する6月間のうち後の5月間に日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと
→最初の1ヶ月に給付金を受けていても、その月の分は未使用なので、後5ヶ月となっています。
高年齢求職者給付金、就職促進給付、教育訓練給付、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、雇用保険二事業(就職支援法事業を除く)に要する費用については、国庫負担は行われない。
→「高年齢」と宗教(しゅうきょう「就職促進給付」「教育訓練給付」)は国庫負担なしです。雇用保険二事業は完全に国庫負担がないわけではありません。
徴収法
認定決定された概算保険料は納付書、認定決定された確定保険料は納入告知書。
→納付書と納入告知書の違い分かりますか?
増加概算保険料については、認定決定は行われない。
→そのまま覚えましょう。
メリット収支率の算定基礎に、労災保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものは含める。
→含めます。第3種特別加入と混同しないよう気を付けましょう。
特別加入保険料算定基礎額は、厚生労働大臣が定めた額の中から、特別加入者本人が申請の際に希望する額に基づいて、「厚生労働大臣(都道府県労働局長に委任)」(×労基署長)が決定した特別加入者の給付基礎日額を365倍した額とされている。
→3,500~25,000円のやつです。
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、遅滞なく(×14日以内)、労働保険事務等処理委託届を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
→「事務処理委託届」を「遅滞なく」です。他に「解除届」や「60日前」など、労働保険事務組合は混同しやすい論点が何気に多いです。定款の変更は14日以内、廃止届は60日前など。
労働一般
争議行為が発生したときは、その当事者は、直ちにその旨を労使委員会又は都道府県知事(×厚生労働大臣 ×都道府県労働局長)に届けなければらない。(労働関係調整法)
→公益の事業の場合は?
就業構造基本調査は総務省によって実施される。
→「賃金構造基本調査」は厚生労働省です。
雇用動向調査は一般統計調査であり、年2回実施される。
→他に「基幹統計調査」もあります。
健康保険法
2以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認(×認可)を受けて、当該2以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。(法34条)
→労災の複数事業労働者は「事業主が同一人でない」です。
食事療養に要した費用は、保険外併用療養費の支給の対象となる。
→入院時とは書いておらず、普通に「食事療養」です。高額な健康食品とか?
厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率の変更の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
→協会から変更が上がってきますので、認可したら告示します。
適用事業所に使用される被保険者が傷病手当金を受けるときには、老齢基礎年金及び老齢厚生年金との調整は行われない。
→労災も似たような規定ありましたね。
「一般保険料率」は、「基本保険料率」と「特定保険料率」を合算したものである。
→覚えましょう。日雇特例被保険者は「平均保険料率」です。
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。(法117条)
→酔っぱらって怪我したら、給付されないこともあるのか。。
高額介護合算療養費の額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に、介護合算按分率を乗じて得た額である。
→健康保険と介護保険の自己負担額を元に按分します。
健康保険組合は、特定健康保険組合の認可を受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上(×4分の3以上)の多数により議決しなければならない。認可の取消しを受けようとするときも同様である。
→健康保険組合の合併・分割・解散は3/4以上です。では何の3/4でしょうか?
健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければ(×認可を受けなければ)ならない。
→届出でOKです。では協会は?
指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について、介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の指定、指定地域密着型サービス事業者の指定又は指定介護予防サービス事業者の指定があったときは、その指定の際、当該訪問看護事業を行う者について、指定訪問看護事業者の指定があったものとみなす。
→みなします。
保険者は、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があったときは、その費用の請求に関する審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会(×健康保険組合連合会)に委託することができる。
→覚えましょう。
事業主は、その氏名、名称、住所に変更があったとき又は事業所の名称、所在地に変更があったときは、「適用事業所所在地・名称変更(訂正)届」等を「5日以内」(×遅滞なく)に、厚生労働大臣(日本年金機構)又は健康保険組合に提出しなければならない。
→「遅滞なく」ではありません。
国民年金法
法92条の2(口座振替による納付)の規定による申出の受理及び承認の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されており、厚生労働大臣が自ら行うことはできない。
→厚生労働大臣が行うことができないなんて、なかなか珍しいと思います。権限を委譲しても「自ら行うことを妨げない」ことの方が多いかなと。
妻が障害基礎年金の支給を受けたことがあっても、寡婦年金の受給権は発生する。
→夫が障害基礎年金の支給を受けたことがある場合は受給できません。
第1号厚生年金被保険者の被扶養配偶者である妻であって、昭和61年法改正前に国民年金に任意加入していたものに支給する老齢基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額を上回ることがある。
→妻の老齢基礎年金が満額でも、振替加算には影響しません。
日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、厚生年金保険の被保険者資格を取得したときは、当該取得日に任意加入被保険者の資格を喪失する。
→特例任意加入被保険者が老齢又は退職を事由とする年金給付の受給権を取得したときは、翌日に喪失します。紛らわしいですね。。
日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、国民年金基金の加入員となることができる。
→特例任意加入被保険者は、加入することができません。
国民年金基金が支給する年金及び一時金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基いて、国民年金基金(×国民年金基金連合会)が裁定する。
→そのまま覚えましょう。国民年金基金が裁定します。
国民年金基金が徴収する掛金の額は、掛金の額の上限の特例に該当する場合を除き、1月につき68,000円を超えることはできない。
→特例の場合は102,000円が上限です。
厚生年金保険法
実施機関(厚生労働大臣を除く)は、毎年度、拠出金(×納付金)を納付する。
→国民年金も含めて、お金の流れは押さえておきましょう。選択式での出題が怖いです。
厚生年金保険法による年金たる保険給付の額(×保険料率)は、国民(×労働者)の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
→こちらも国民年金含めて、選択式対策をしましょう。
老齢厚生年金の額にかかる平均標準報酬額(×)とは、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、再評価率(×)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。
→これも選択式対策をしましょう。
老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となる配偶者が、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、当該加給年金額は支給停止される。
→加給年金=家族手当 と考えると、既に厚年からサービスを受けているなら払いませんよというイメージです。
障害手当金の支給要件:初診日から起算して5年を経過する日までの間において、傷病が治っていること。
→治っていることが要件です。
被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、妻の遺族厚生年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、支給停止される。
→前妻の子と、後妻の例です。通常は妻の方が優先順位が上ですが、この場合は妻の遺族厚生年金が支給停止されます。
受給権者が65歳に達しているときは、旧国民年金法による障害年金と遺族厚生年金は併給することができる。この場合、遺族厚生年金の額に経過的寡婦加算が加算されているときは、当該経過的寡婦加算に相当する額は支給が停止される。
→経過的寡婦加算が遺族基礎年金に付属するものだと考えると納得しやすいかと思います。
離婚時の分割請求により標準報酬が改定された第2号改定者について、当該改定を受けた標準賞与額は、当該第2号改定者がその後60歳台前半の在職老齢年金の受給権者となった場合においても、総報酬月額相当額の計算の対象とはならない。
→改定前の標準賞与額を用います。
加給年金額の加算要件(被保険者期間240月以上)には、「離婚時みなし被保険者期間」および「被扶養配偶者みなし被保険者期間」は含まれない。
→「離婚時みなし被保険者期間」が加算されるものには何があるか答えられますか?
「特定適用事業所」とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が1年間のうち6箇月以上常時50人を超えるものの各適用事業所をいう。
→これまでは100人超でしたが、2024年10月に改正されました。
社会一般
社会保険労務士法人の解散及び清算は、裁判所(×大臣 ×社労士連合会)の監督に属する。
→裁判所です。他に裁判所が登場するのは労基の付加金と、厚年の離婚分割ぐらいでしょうか。
高齢者医療確保法によると、保険者及び後期高齢者医療広域連合は、共同して、加入者の高齢期における健康の保持及び医療費適正化のために必要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のため、都道府県(×市町村)ごとに、保険者協議会を組織する。
→都道府県ごとに必ず設置します。義務です。国保はすべての市町村に「国民健康保険運営協議会」が置かれます。
個人型年金加入者とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。
→確定拠出年金の個人型の定義です。
企業型年金加入者の拠出限度額について、他制度加入者以外のものである場合は、各月につき、55,000円である。
→確定拠出年金です。企業型のみの限度額、企業型+他制度、個人型+企業型などバリエーション豊富ですが覚えましょう。
確定給付企業年金法によると、老齢給付金に係る規約において、20年(×10年)を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならないこととされている。
→「20年」はなかなか珍しい数字かなと思います。
*
以上、計81項目でした。ちなみこちらは予備校の掲示板に「今日の一言」として投稿したものの再掲になります。
掲載日:4/17~7/9 84日ですが重複があったため81項目です。
余談ですが、SNSもなかなか良いですね。
勉強にSNSは否定派でしたが、時間を費やしすぎなければ、有益な情報が得られたりフォロワーさんの頑張りに励まされたりとメリットだらけです。
社労士になりたいブログパープル2.png)